子どもののどが真っ赤になって熱が出た、こんな症状の場合、インフルエンザや新型コロナウイルスによる感染が真っ先に浮かぶかもしれません。でも、もしかすると溶連菌感染症かもしれません。溶連菌感染症は、新型コロナなどのウイルス性の疾患と違って、適正な抗生剤による治療が重要な疾患です。
子どもののどが真っ赤になって熱が出た、こんな症状の場合、インフルエンザや新型コロナウイルスによる感染が真っ先に浮かぶかもしれません。でも、もしかすると溶連菌感染症かもしれません。溶連菌感染症は、新型コロナなどのウイルス性の疾患と違って、適正な抗生剤による治療が重要な疾患です。
令和7年賃金構造基本統計調査の実施についての協力依頼について
保護中: 7/6 健康サポート薬局研修B 資料等について【委員用】
【更新】令和7年度 認定実務実習指導薬剤師養成講習会【更新講習】の開催について
【養成】「令和7年度 認定実務実習指導薬剤師 養成研修会」の開催について
2025.8.3令和7年度 注射剤の無菌製剤処理研修会開催案内

標記の件について、厚生労働省政策統括官より協力依頼がありましたので、 調査票が届いた場合には、ご協力いただきますようお願いいたします。 20250704事務_令和7年賃金構造基本統計調査の実施についての協力依頼について

このことにつきまして、日本薬剤師会より連絡がありましたのでお知らせいたします。 20250627総6_「災害医療・薬事対応に関する研修プログラム」の研修プラットフォーム提供開始のご案内及び研修実施について(依頼) ※本フ
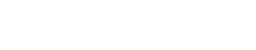
© 2021. 三重県薬剤師会 All Rights Reserved.